討議にどのような役割があるのでしょうか。討議は倫理に不可欠なのでしょうか。
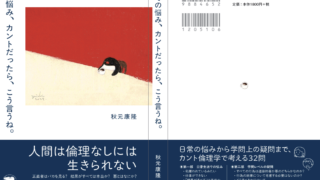 カント倫理学
カント倫理学 『その悩み、カントだったら、こう言うね。』
本では世間の人が抱えるであろう悩みに答えていくことで、カント倫理学が私たちの生きる指針たりうるかということを示していきます。とはいえ、カント倫理学には不十分なところがあることも事実です。その点は後世を生きる私たちが手を加えていかなければなりません。本書では、そこまで踏み込んでいます。
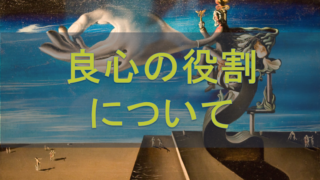 カント倫理学
カント倫理学 良心の役割
カントは良心の働きについて、内的な法廷における原告の役割を担うものとして説明します。しかし、同時に、裁判官の役割も担うと言うのです。原告と裁判官が同一人物というのは問題ないのでしょうか。またカントは、理性が原告と裁判官、感性が被告の役割を担うと言います。しかし、理性と感性の間に本当に線引きなどできるのでしょうか。これらの疑問に対峙しながら(カントの考える)良心の役割について明らかにしていきたいと思います。
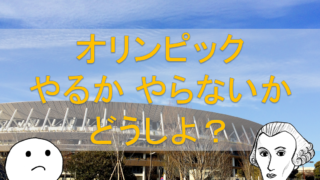 カント倫理学
カント倫理学 オリンピックのゴタゴタを見て、カントは何を言う
良心が誤りを犯すといったことがありうるのでしょうか。暴走するといったことがありうるのでしょうか。2021年東京オリンピック開催の是非を巡る議論に絡めて、カントの思想を頼りに、この問いに対峙してみたいと思います。
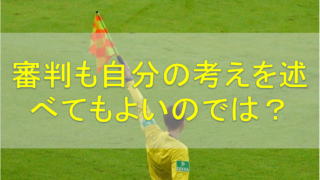 カント倫理学
カント倫理学 審判の説明義務について
なぜブンデスリーガの審判は自分の裁いた試合の判定の根拠について口にしないのでしょうか。メディアは話を聞こうとするはずであり、出てこないということは、上(ドイツサッカー協会か審判組織?)が止めているのか、もしくは、本人が避けているのだと思います。しかし、そんなことをすることにどんなメリットがあるのでしょうか。私は負の側面の方が大きいと思っています。
 カント倫理学
カント倫理学 道徳判断を誤る可能性について
行為者本人は自分の道徳判断について正しいと思っているものの、周りの人間はその判断を間違っていると思っているような場合、その正当性はどうなるのでしょうか。
 カント倫理学
カント倫理学 倫理に討議(話し合い)は必要か?
カント倫理学は他者との討議が欠けているという批判があります。では討議を導入すれば問題が解決するのでしょうか。