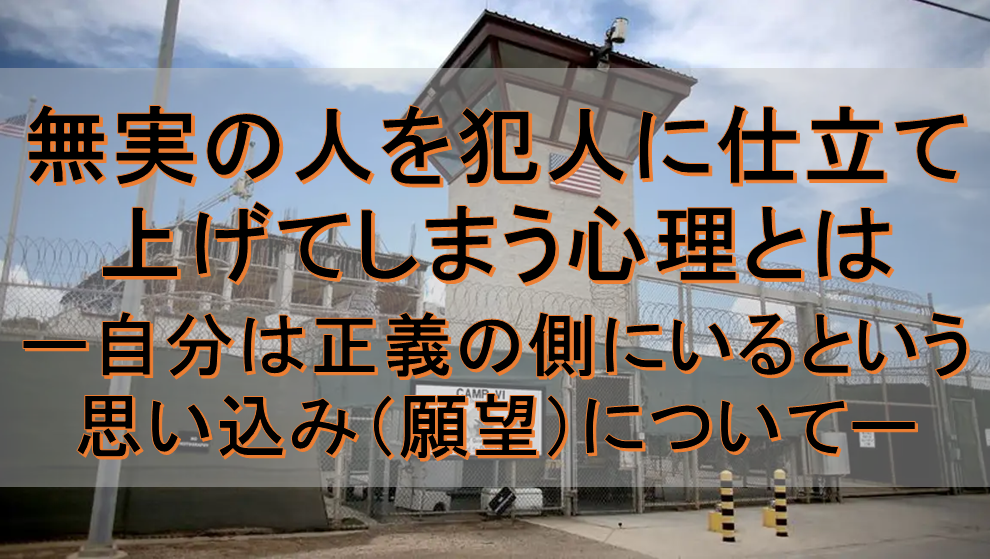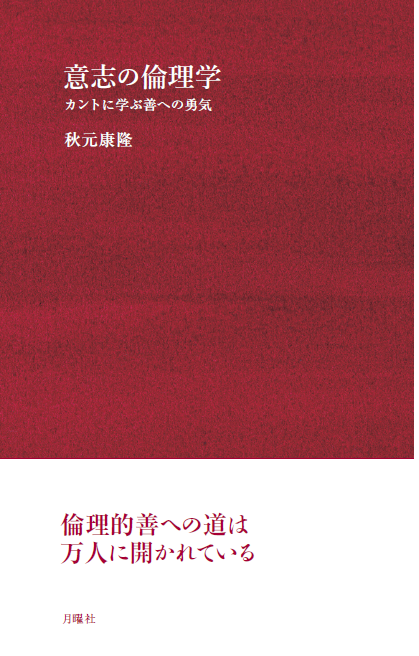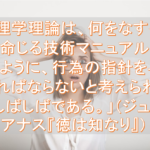前回の記事において、自殺や嘘も道徳的悪であるとは決めつけられないという話をしました。なぜそう言えるのかということですが、まずそのような自殺だの嘘だのといったラベルが何を指すのか判然としない点が挙げられます。例えば、自殺について言えば、命がけの危険な仕事があります。それが危険であればあるほど、自殺との境目がはっきりしなくなっていくわけです。嘘に関して言えば、もっと頻繁に触れているはずであり、抽象的に発言すること、つまり、グレーゾーンなどいくらでもあるわけなのです。加えて、この種の議論で必ず出てくるのは(厚)化粧はどうなんだとか、カツラはどうなんだといった話です。そんなことを考え出したら切りがなく、明確な線引きなどできないことに思いが至るはずなのです。
そして、もうひとつの理由ですが、前回の記事では触れなかった論点をここに挙げると、道徳性は行為者の内面であるところの動機や意志や行為原理のうちにあるのであって、行為そのもののうちにはない点を付け加えることができます。カントは以下のように述べています。
それはそこにおいて多かれ少なかれ働く余地を有しており、それについての限界は、はっきりとは設けられない。法則は、ただ行為原理にのみ妥当するのであって、特定の行為に対しては妥当しないのである。(カント『人倫の形而上学』)
カントは普遍化の思考実験をすべきことを説きます。それは自分の行為原理を万人が従った世界を想像し、それが望ましいものであるかどうかを吟味する思考実験のことです。この思考実験には「正解」「不正解」はありません。自分が正しいと思ったものが正しいのです。「いかに行為すべきか」という問いの判断は個々人の選択意志に委ねられているのです。
このようなカントの考え方のうちにはひとつの前提があります。それは、わたしたちは万人が理性を有しており、真剣に考えさえすれば、誰もがまっとうな判断を下すことができるはずであるという前提です。学や知識などなくとも、何をすべきだり、何をすべきでないかということは、分かるはずであるということです。
ここまで話が及ぶと、とんでもない行為、例えば、「ヒトラーの行為も道徳的に正しかった可能性があるのか?」といった、お決まりの反論が出てくるのですが、それに関連することは自著において、ユダヤ人を大量に強制収容所に輸送することに加担したアドルフ・アイヒマンと絡めて書いているので、興味がある人はそちらを参照してください。
また現在出版準備を進めている本において、大量殺人を犯しておきながら、自らの正当性を説いた極めて特異な人物、植松聖に対して考察を加えるつもりでいます。こちらは発売までもう少しお待ちください。
冤罪事件
今回の記事では、そこまで極端ではなく、本当に自身の悪性について自覚していたのかどうか微妙なケースを取り上げたいと思います。具体的には、冤罪事件(もしくはその可能性が高い事案)に関わった人々に関するものです。
紅林麻雄のケース
紅林麻雄とは、終戦直後に静岡県において、被疑者に長時間の拷問を加え、自白させるこよによって、多くの冤罪事件を引き起こした元警察官です。

著作家の管賀江留郎氏は膨大な資料をもとに、紅林刑事が起こしたさまざまな冤罪事件について本にまとめています。ただ管賀氏の紅林刑事に対する姿勢は、私の目からはいささか好意的過ぎるものとして映ります。一例を挙げると管賀氏は、紅林刑事は決して意図的に犯人を捏造しようとしていたのではなく、その者が犯人であると心底信じていたのではないかと見ています(440頁参照)。しかし、この文の前後にそう言える根拠は見当たりません。似たような文面として「明らかに事実と反することを平気で書くという点から見ても、そう〔=犯人を捏造する気などなかった〕としか理解できない」(38頁)といったものもありますが、論旨が飛躍しているのではないでしょうか。事実に反することを平気で言うことと、犯人を捏造する気などなかったことの間には因果関係などないはずです。
むしろ、紅林刑事の同僚であった南部清松氏が分析しているように、浜松事件において棚ぼたで評価されてしまったため、その後も事件を解決し続けなければならないことへのプレッシャーから犯人を次々と捏造していった(33頁参照)というのが実情に近いのではないでしょうか。だとすれば、そこにあるのは管賀氏の言葉を借りれば「肥大化した自己像を満足させるため」(34頁)という利己的な都合であることになるのではないでしょうか。
そのずさんなやり方から紅林刑事が容疑者たちを本心から犯人と考えていたと受け取るには無理があると思うのです。例えば二俣事件では、ただ近くに住む素行不良な若者というだけの理由で補導され、その後、四日間も暴行された上、無理やり自白させられています(21頁参照)。しかし実際には、その人物にはアリバイがあるし、返り血も浴びていなければ、現場に残っていた足跡の大きさも合わないのです(22頁参照)。ただ無茶苦茶なだけであれば、「紅林という人物は論理的思考力のない人」という説明も可能なのでしょうが、紅林刑事は非常に理性的な態度で偽装工作にあたってもいるのです(30頁以下)。確信犯で事実を捏造していると見るのが自然なのではないでしょうか。
ただ、仮に無関係の人を犯人に仕立て上げようとしていることへの自覚があったとしても、それが直ちにその者が自らのしていることを道徳的問題として意識し、道徳的悪を犯していたとまでは結論付けることはできません。そこまで考えが及んでいなかった可能性は十分にあると思います。
道徳的悪の可能性が高い案件については本記事の後半に触れることになります。
グアンタナモ刑務所での出来事
グアンタナモ刑務所では、収監されている者が非人道的な扱いを受けていたことは、日本でも周知のことでしょう。モハメド・ウルド・スラヒのケースはそこに収監されていました。通話記録などから、彼がビンラディンをはじめとするアルカイダの主要メンバーとのつながりがあることが分かっていたからです。しかし、彼自身は自分がテロに加担したことを認めません。いくら拷問されても口を割らないのです。14年間も収監された後、自らが受けた仕打ちについて大々的に発言することによって、グアンタナモ刑務所の実態が世界に知れ渡ることに一躍買ったのです。
ここに彼に関するドキュメンタリービデオのURLをアップしておきます。私自身この映像を観て、即座に紅林刑事との類似性や、カント倫理学との関連性について考えるに至りました。
ドキュメンタリーにはさまざまな人が出てきますが、ここでは二人に焦点を絞りたいと思います。まず刑務所の責任者であった「ミスターX」と言われる人物です。
ミスターX
グアンタナモ刑務所の責任者であったミスターXは自ら拷問をしていたわけでも、部下に指示を出したわけでもありません。この点で拷問を自ら命令していた(32頁参照)紅林刑事とは決定的に異なります。ただし、ミスターXも部下がスラヒに拷問をしていたことは知っていました。

ミスターXはグアンタナモ刑務所を去った後、自分が上司でありながら、長年拷問を黙認していたことを恥じ、苦しむようになります。ただ興味深いのは、ミスターXはスラヒがテロの容疑者であることを最後まで強く信じている点です。つまり彼は、スラヒは容疑者としては黒であるものの、しかしながら自分が彼(ら)に接してきた態度は誤りであったことを認めているということです。
自らが犯したことを悔いている。これが道徳的悪の告白と受け取れるかもしれませんが、カント倫理学の建てつけからは、そうは言い切れません。もし自分が行為をなしている際には、その行為原理が普遍化を意欲できないと自覚していたわけではなく、それが事後であったならば、そこに悪性を見出すことはできないためです。
道徳的悪の疑いが強いのは、むしろその上司であるリチャード・ズーリ(Richard Zuley)の方です。
リチャード・ズーリ
スラヒから自供を引き出せないことから、ズーリはその専門家として招集され、ミスターXの上司になりました。泣く子も黙る「シカゴ警察」の元敏腕刑事です。
ドキュメンタリーではズーリ本人も出てきて、インタビューに答えています。スラヒが自らの体験について積極的に発信しているのを受けて、それに反論するつもりで出てきたのだと思われます。添付したビデオの52分を過ぎた辺りから彼へのインタビューがはじまります。

いくら拷問をしても「知らない」の一点張りのスラヒに対して、ズーリはある案を考え出します。スラヒには大切な母親がいます。そこで彼女を利用することにしたのです。具体的には、スラヒに手紙を渡したのです。そこには男性囚人たちの群れのなかにスラヒの母親を入れるつもりであることが書かれていたのです。
それを目にしたスラヒは態度を一変させます。突然ものすごい勢いで「自分の知っていること」について話しはじめたのです。この時点では作戦がうまくいったように見えました。ズーリもインタビューでは「よく考えた作戦だろ」と言わんばかりに得意げに語るのです。
しかし、スラヒの供述内容は、それまでFBIやCIAが持っていた情報にまったく符合しないものでした。そのため嘘発見器にかけることになりました。すると、スラヒの供述はまったくの作り話だったことが明らかになったのです。
そもそもまったく関係ない母親を男性囚人のなかに入れるだとか、それをネタに自白を引き出すとか、そんな方法が許されるはずがありません。そのことをインタビュアーが触れると、「私たちはそんなつもりで吹き込んだのではなく、スラヒが勝手にそう解釈したのだ」と言い張るのです。あまりに無理のある言い訳です。脅すつもりでなかったのであれば、なぜそんな作り話を吹き込んだのか、その意義がなくなってしまいます。
ひょっとするとズーリはグアンタナモ刑務所で職務に就いているときも、そして、アメリカに帰ってきてからも、もっと言えば、インタビューを受けている間も途中までは、自分の正しさを信じていたのかもしれません。しかし、インタビューを受けている間に彼のなかで変化が起こっていることを私たちは画面越しに見て取ることができるのです。
ズーリの態度は次第に不機嫌になっていき、放送禁止用語を吐いて、インタビューを一方的に打ち切ろうとします。私の目には、彼が自分にとって都合が悪いことであることが分かっているから、カント的な言い方をすれば、自分の行為原理が普遍的な視点から意欲されないものであることを自覚しているから、そのような態度に至ったように見えるのです。もし都合が悪いという思いに至ったのであれば、自らの落ち度を認めて謝罪すべきなのです。それをせずに誤魔化して、逃げるような態度のうちに、私は悪の影を見るのです(ただしそれでも100パーセント確実に悪であるとまで私は言うつもりはありません。彼の内面を正確に把握することはできないためです)。
まとめ
ミスターXもズーリも自分がアメリカのために自分の人生を捧げてきたことを旨を張って主張します。彼らは決して悪魔であるわけではなく、祖国のために戦った自覚があるというのは嘘偽りない気持ちだと思います。しかし、その気持ちが先走り過ぎてしまうと、罪のない人に罪を着せる、不法な手段に訴えるということにつながってしまうのです。
紅林刑事の冤罪事件に関しても、彼がずさんな捜査や自白の強要が明らかになり裁判結果が次々と覆されていった後も、反省の色を見せることなく、この世を去ってしまいました。本人がすでにこの世にいない以上、彼自身が制裁を受けることはありません。そのため、紅林刑事のやったことを知った人のなかに、彼の親族を誹謗中傷したり、さらには脅迫まがいのことをする人たちが出てくるのです。不当に苦しめられた人を見て、その原因を作った人物に社会的制裁を加えたいと感じる気持ちは分からないではありません。しかし感情から行動に移すのではなく、理性を用いて考えてほしいのです。紅林刑事が罪もない人を犯罪人に仕上げたことと、紅林刑事の親族であるというだけで社会的制裁を加えることの間にどれだけの差異があるのでしょうか。