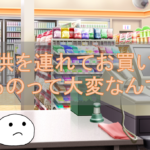カントの哲学は「批判哲学」と称されます。ここで言う「批判」とは、特定の人を批判することではなく、人間一般の理性能力を批判的に吟味することが意図されているのです。つまり「批判哲学」というのは、人間理性の限界にまつわる哲学とも言えます。
理性の有する「限界」の意味
理性の能力を批判するということは、理性の限界を定めるという言い方もできます。そして、ここで言われる「限界」というのは、二つの意味として捉えることができます。
理性に知りえない領域がある
カントの「理性批判」の文脈で、多くの場合に意図されているのはこちらの意味だと思います。
カントが登場する以前、人々は「神は〇〇だ」とか「死後の世界は〇〇だ」などといった、本来は人が認識しえないはずの(彼の用語で言う「超越的な」)事柄について、あたかも知っているかのような態度で語っていました。カントもある時期までは、そのような世界観に浸っていました。しかし、あるときに気づいたのです。実はみんな本当は知らないことについてあたかも知っているかのような素振りで語っているに過ぎないのではないか?と。それ以来彼は、自分が知りえる領域と知りえない領域があること、そして、知りえない領域については理論的な証明が不可能であることを説いたのです。
このように説明すると、至極当たり前のことを言っているだけのように映るかもしれません。しかし、まず当時としては画期的であったと言えます。そして、これは単に歴史的に意義があるというだけではんく、十分に現代的な意義もあるのです。なぜなら今でも自分では認識しえない領域のことを、あたかも知っているような態度で語る人はごまんといるからです。そういう人に対しては警戒すべきなのです。
理性は判断を誤る
「理性批判」の文脈であまり焦点を当てられることがなく、しかしながら、私がここで強調したいのは、むしろこちらの意味です。
例えば、「神が存在してほしい」という願望を持っている人がいるとします。そういう人には、何かの自然現象も「神の仕業として受け止めたい」という欲求を抱くことになります。これが「仮象」を生むのです。仮象とは、漢字に表れているように仮(かり)の象(すがた)のことです。つまり、本当はそうではないのに、そう見えるということです。そして、これは「神がいてほしい」という例からも分かるように、単なる勘違いではなく、必ず願望が含まれているものなのです。この願望が仮象を生み、この仮象が判断を誤らせるのです。
どんなに優秀な人でも、それどころか偉大な先哲カントであろうとも、このようにして判断を誤る可能性があるのです。これは決して感性が原因となっているのではなく、悟性という理性と並ぶ上級認識能力が犯す過ちなのです。
批判哲学の倫理学における意味
カントが批判哲学を論じたこと自体が、非常に画期的で有意深いものであったと私などは思うのですが、さらにもう一段カントのすごい点は、彼は私たちには認識しえない領域があること、そして、誤謬を犯してしまう存在であることを認めながらも、その至らなさが道徳的善をなすことができない、反対に道徳的悪を犯してしまう直接の理由にはならないことを説いた点です。
もう少し正確に言うと、カントは道徳判断というのものは、確かに客観的には誤謬が介在する可能性があるものの、主観的には誤りようがないと論じたのです。道徳性が問題である限り、(普遍化の思考実験によって客観的な視点に立った上での)主観的な正しさへの確信があれば、それで十分なのです。
さいごに
カントは、私のような判断ミスばかりしている人間にも、それは道徳的悪ではないこと、そして、その可能性が常に開かれていることを諭してくれるのです。そこまでしてもらったら無下にできないじゃないですか。